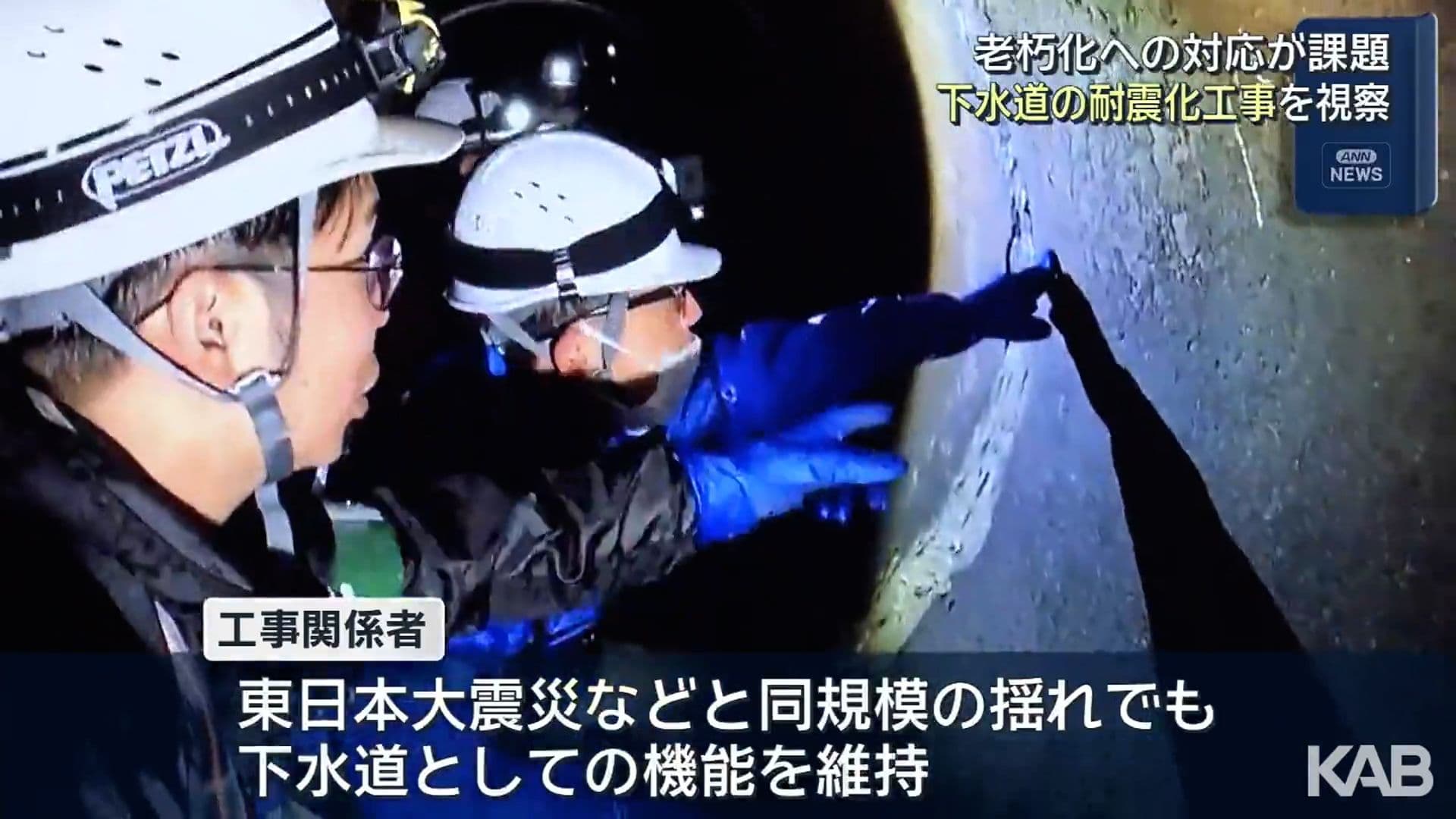
多様性を重んじる「インクルーシブ」という概念が広がりつつあります。障がいのあるなしに関わらず、子どもが一緒に遊べる「インクルーシブ公園」が全国で増えています。
22日から27日までの期間限定で熊本市の水前寺江津湖公園に設置されている「障がいのある子もない子も一緒に遊べるひろば」。運動が苦手、ルールを理解することが難しいなど障がいのある子どもたちでも楽しめる遊具が設置された「インクルーシブ公園」です。
きっかけは子育てで感じた「申し訳ない思い」
この公園の設置を実現させた大塚志津子さん。3人の子どもの母親で、熊本県御船町で発達障がい者を支援するためのNPO法人の代表を務めています。
大塚さんの次男、煌さんは、2歳のときに広汎性発達障がいと診断されました。重度の知的障がいを伴う自閉症で、20歳になった今も、コミュニケーションが苦手などの特徴があるため、意思を伝える際は「ぺクス」というカードを使います。
コミュニケーションをとるのが苦手な発達障がいの子どもたち。子育てには、多くの困難が伴ったと大塚さんは振り返ります。
「一緒に遊べる公園っていうのがないというのが一番の悩み。順番が分からないので滑り台を降りるのに、他のお子さんを突き飛ばす感じで、自分が先に滑ってしまったりすることがあった。危険だなぁ、と思って、他のお子さんに迷惑かけるのは…と」
煌さんが幼いころは、公園で遊ぶことを諦めることも多かったと言います。
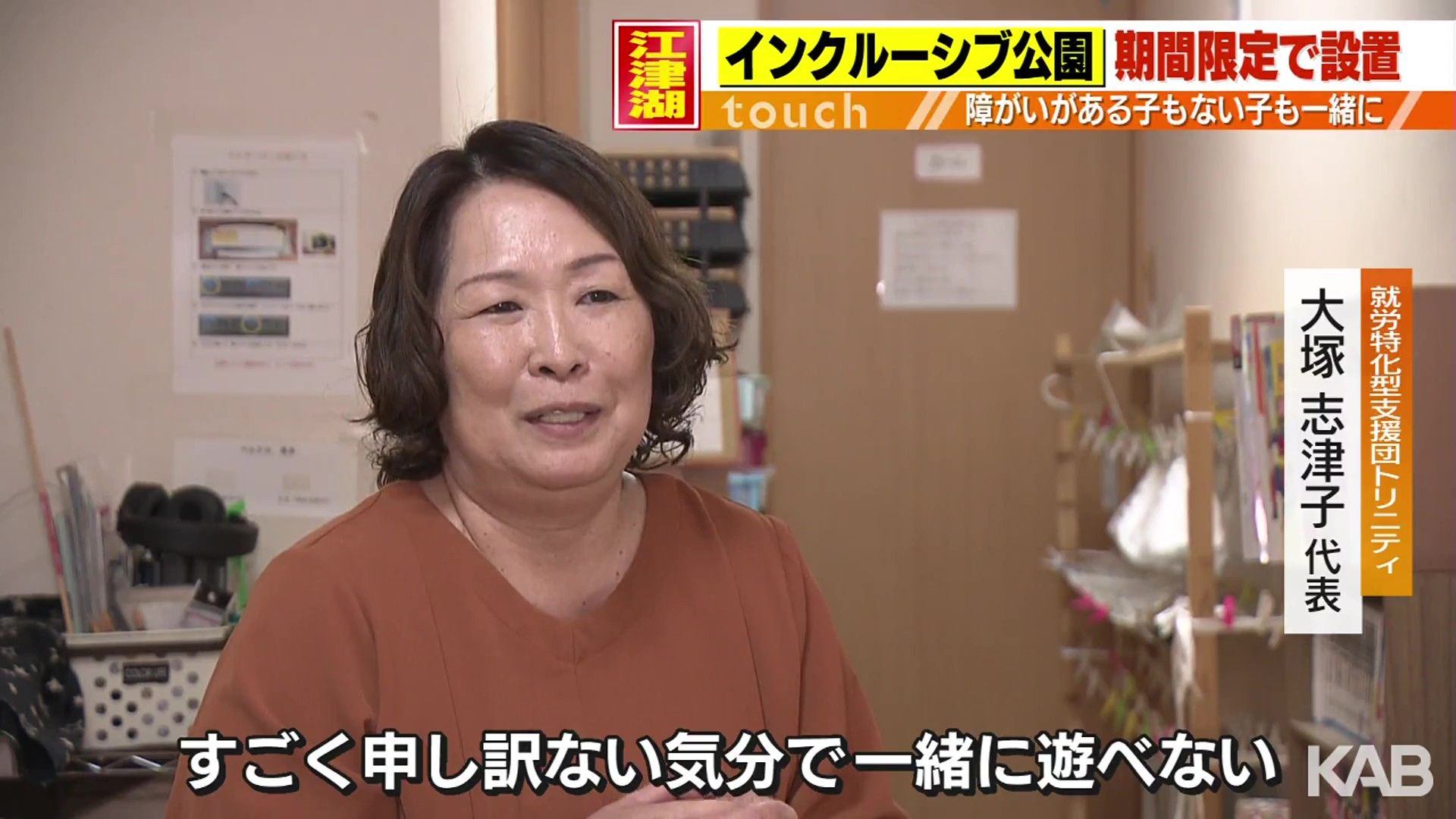
「私は障がいを持っている子どもの側で、こっちから見ると、申し訳ないなと思うけど、反対側の健常な子どものお母さんから見ると『だめよ』とも言えないし(自閉症の子どもを)どう扱ったらいいのか、どう声かけしたらいいのか…すごく申し訳ない気分で、一緒に遊べない」
見て分かるように伝えるなど、視覚支援があると、ルールを理解できることも多いという発達障がいのこどもたち。公園に視覚的な支援があれば、発達障がいがあっても一緒に遊べるのではないか、という思いから応募した「公園・夢プラン大賞2023」で最優秀特別賞を受賞し、公園の設置が実現しました。
「インクルーシブ、共存、共生できる場所を」
今回、期間限定で設置された「障がいのある子もない子も一緒に遊べるひろば」。握力がなくても乗れるブランコ、適正な歩幅で歩く練習ができる平均台など、障がいのある子どもたちに配慮し8つの遊具が設置され、早速、多くの子どもたちが遊ぶ姿が見られました。
こども支援室みらい若葉教室の石田由加利さんも「遊具にルールが書いてあるので、声をかけてから回そうねとかあると、子どもたちも理解して安全に遊べるなって思いました」と話します。
大塚さんは「インクルーシブ公園」をきっかけに、障がいのある子どもへの理解を深めて欲しいと考えています。

「自分とは違う子と触れ合うことで、こういう子もいるんだ、自分とは違うということを、それが普通で当たり前で日常というのを公園の中で学べたらいいなと思います。私の願いとしては公園から始まって、いろんな場所でインクルーシブ、共存、共生できるような場所が、たくさん増えてくれたらいいなと思っています」












