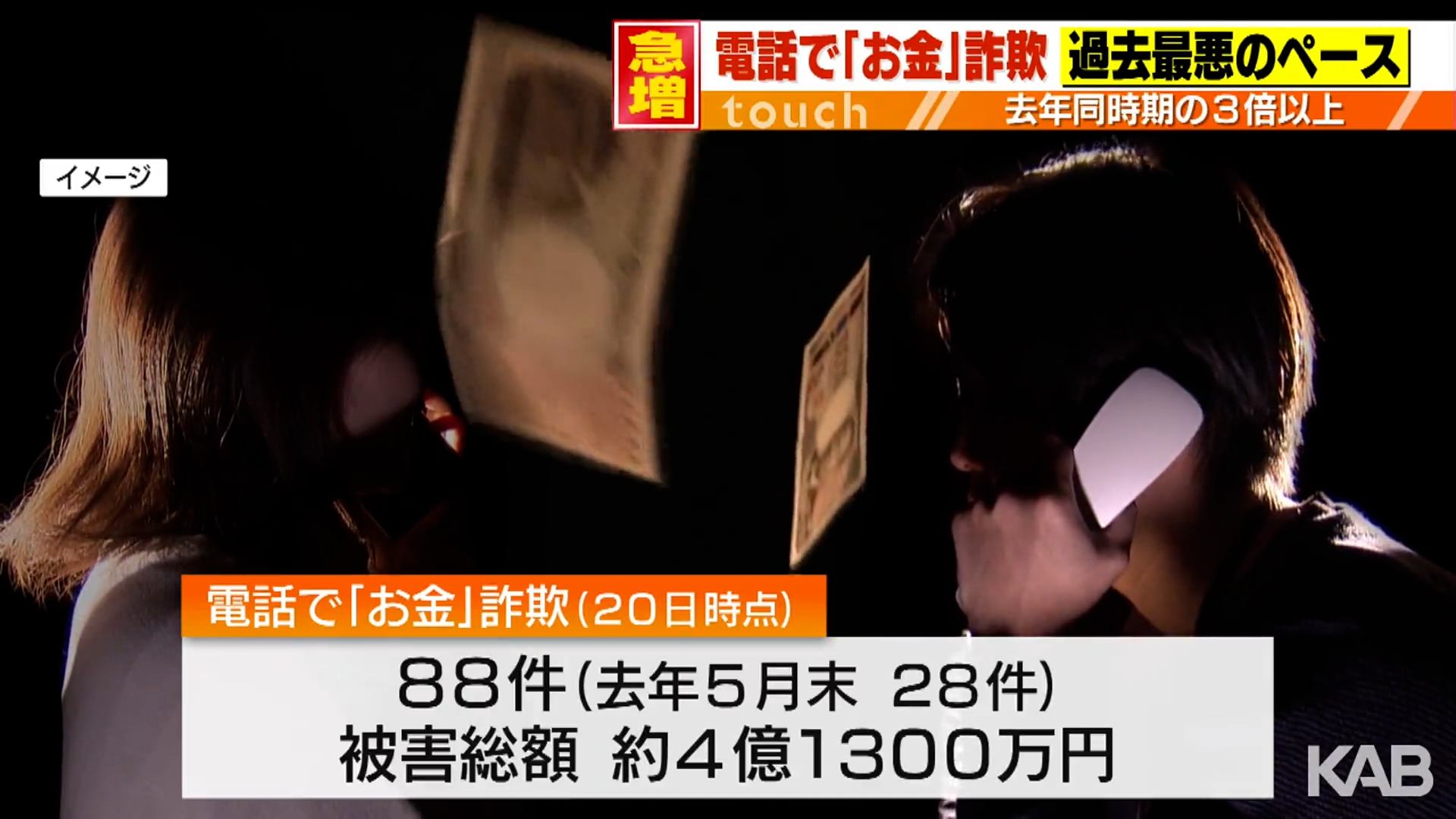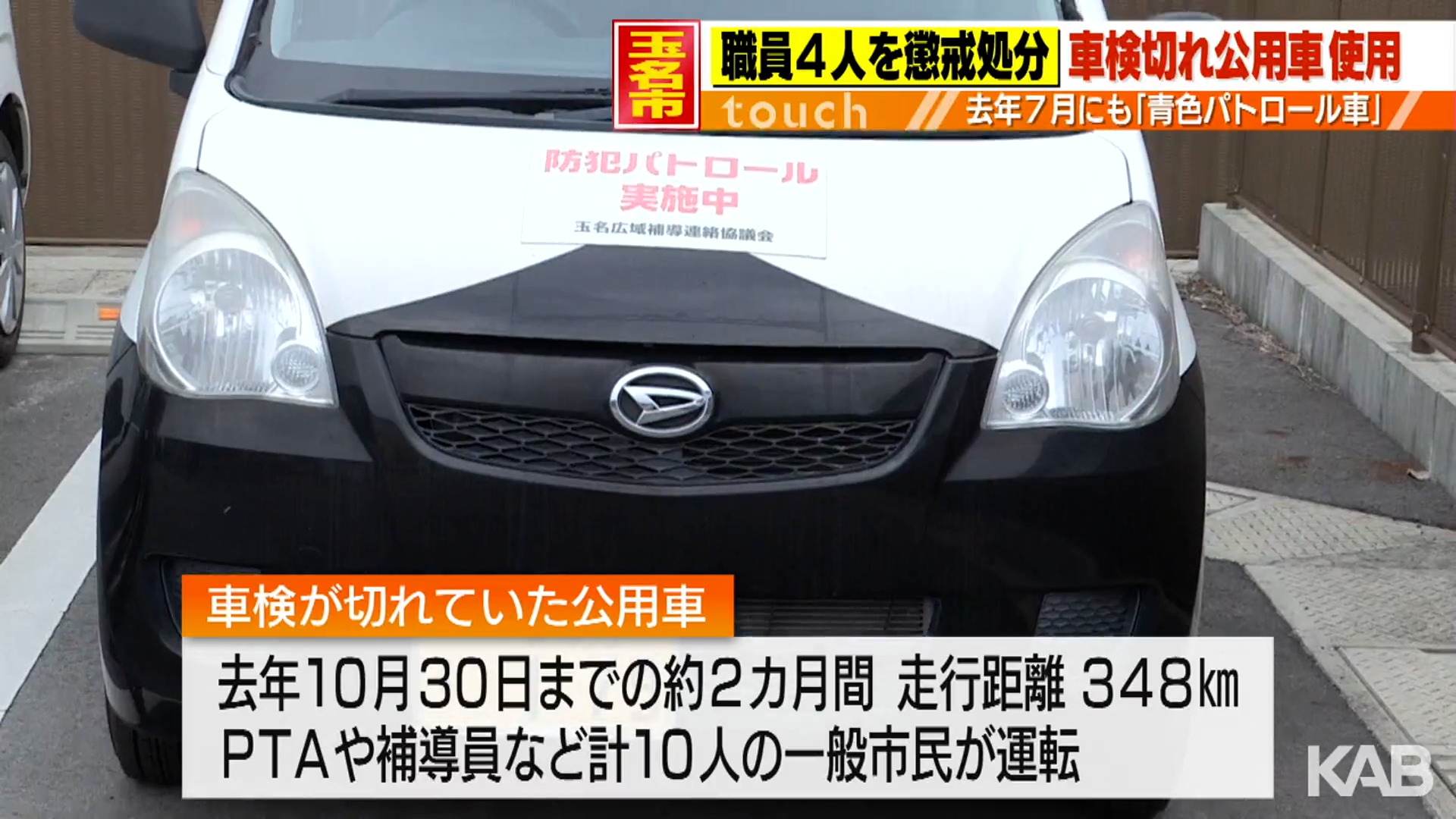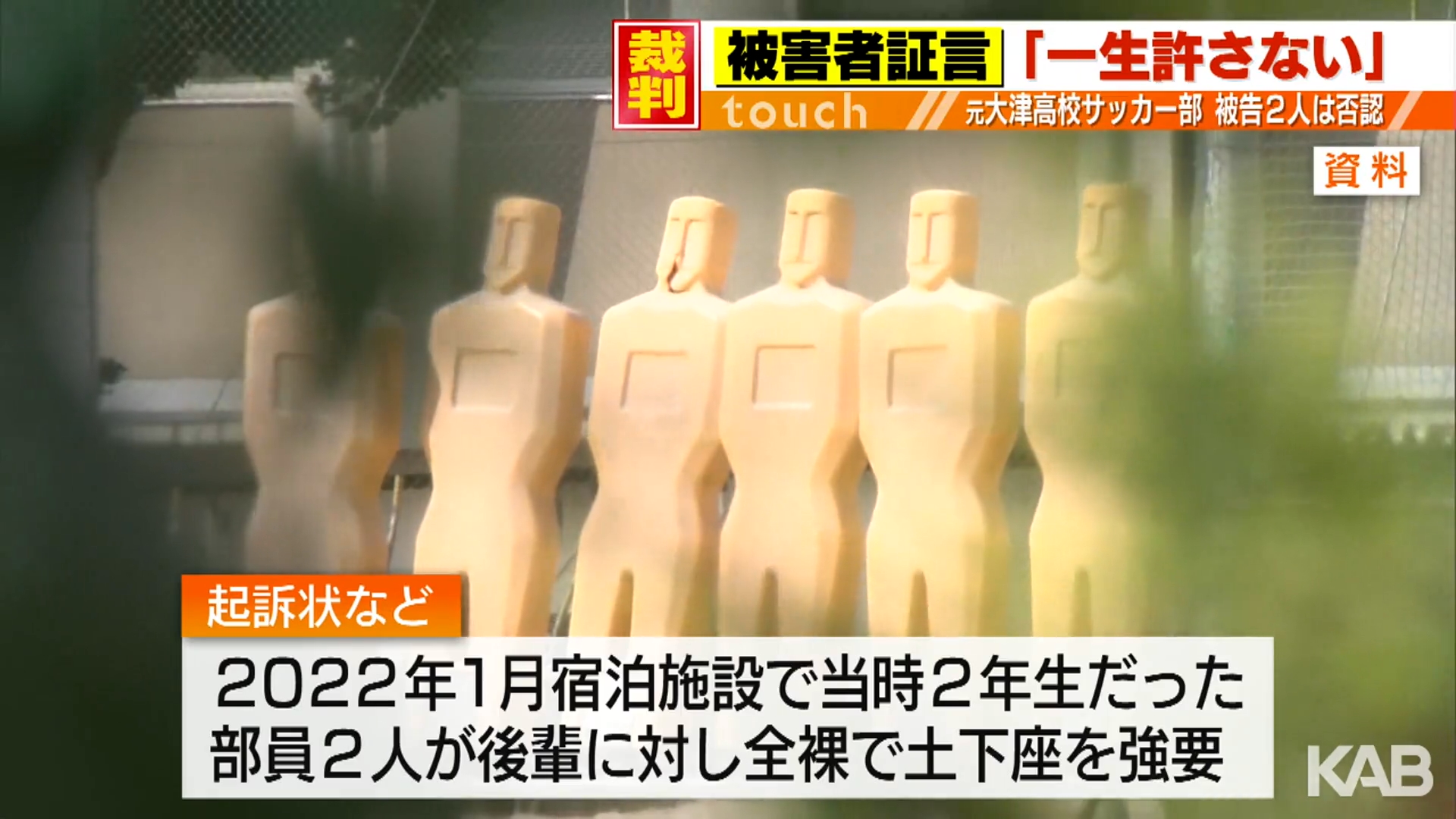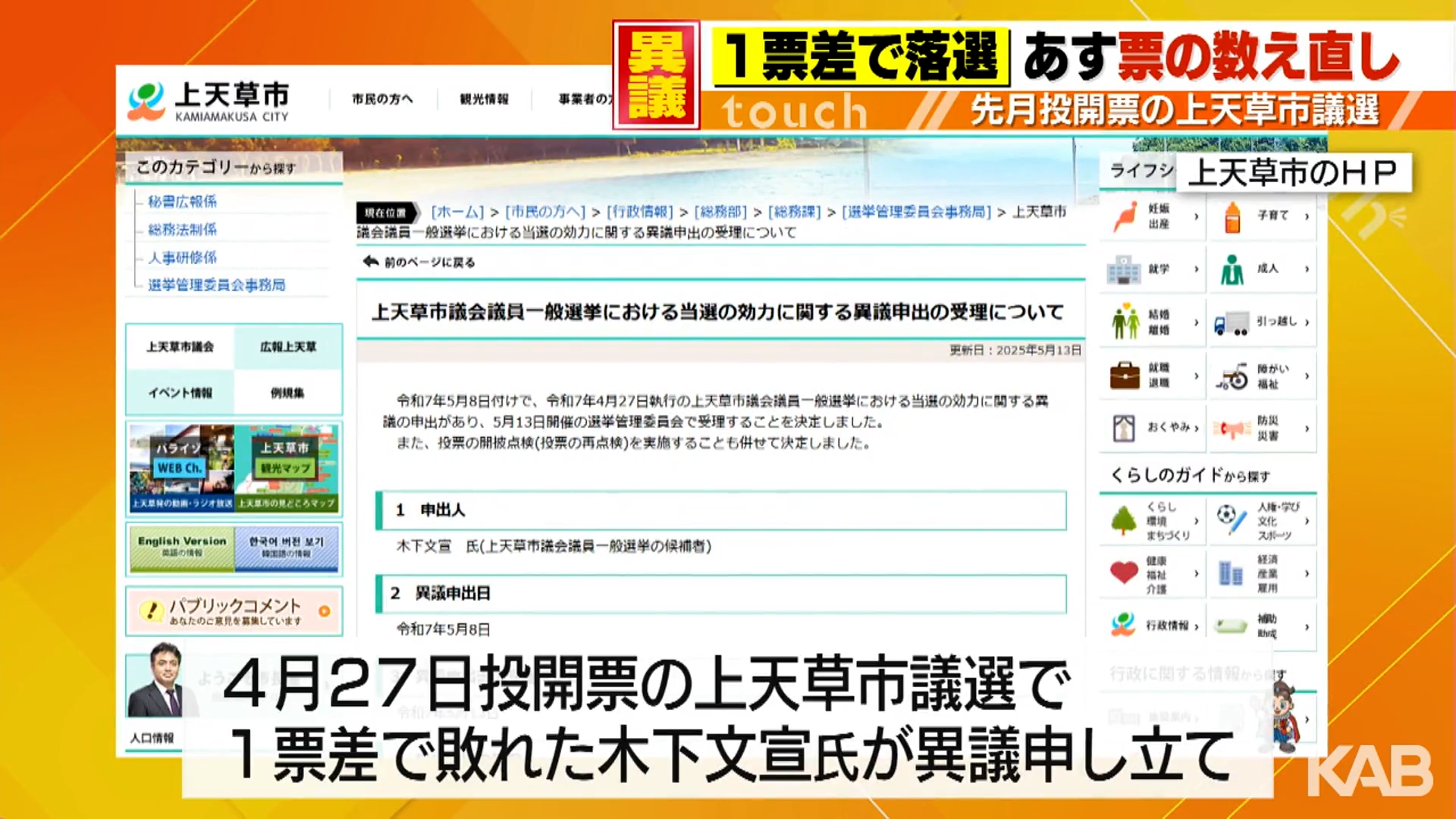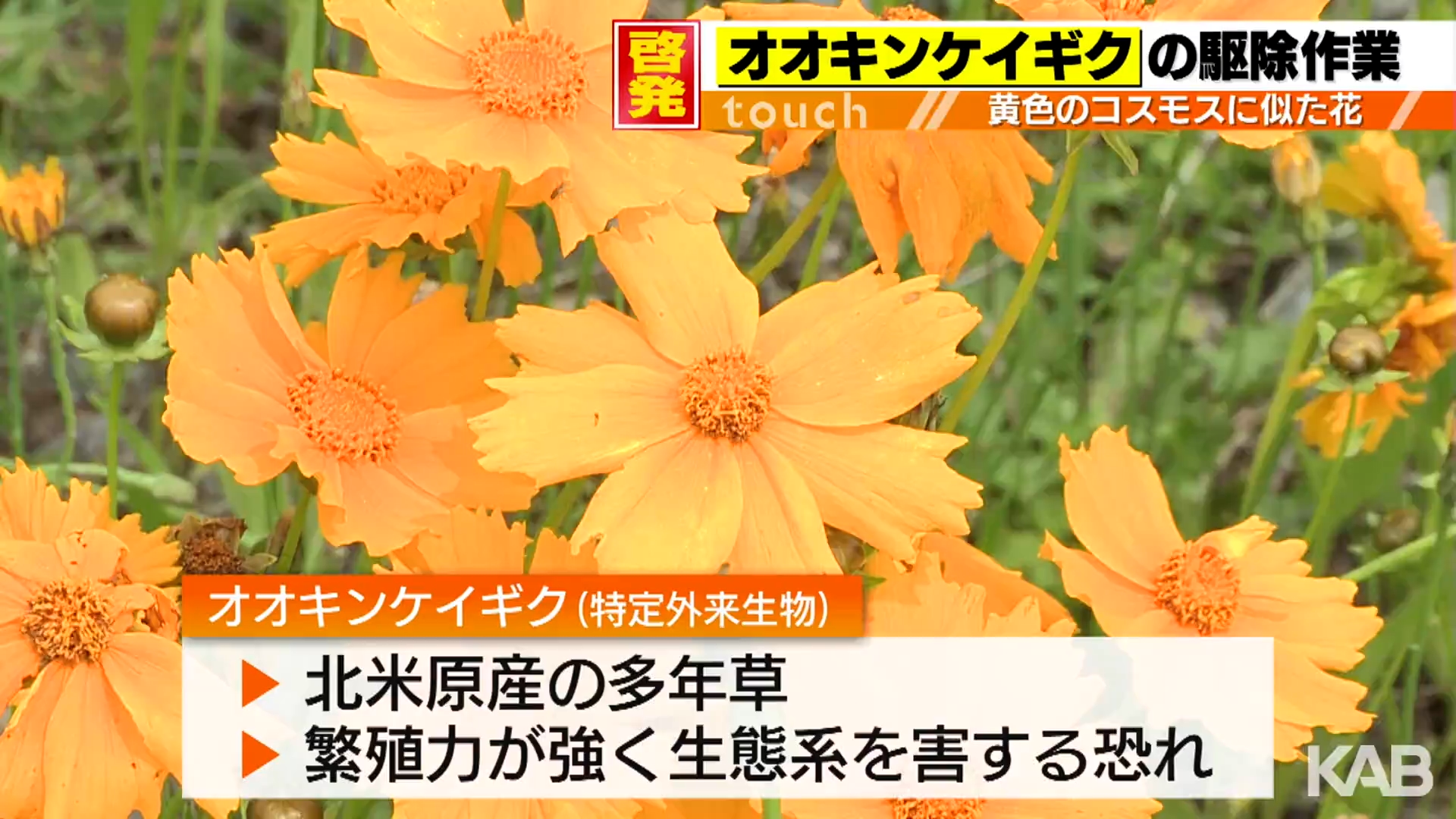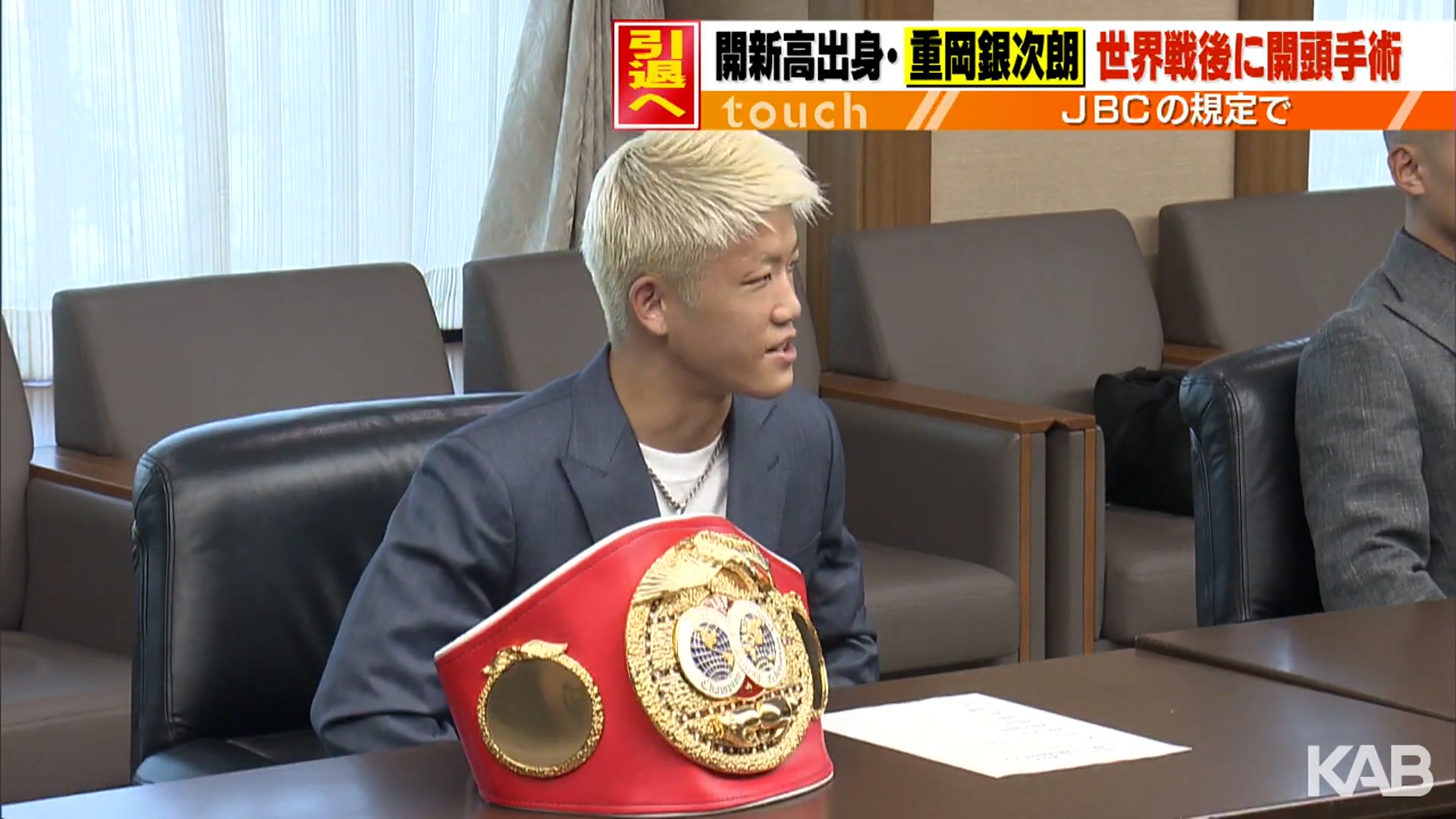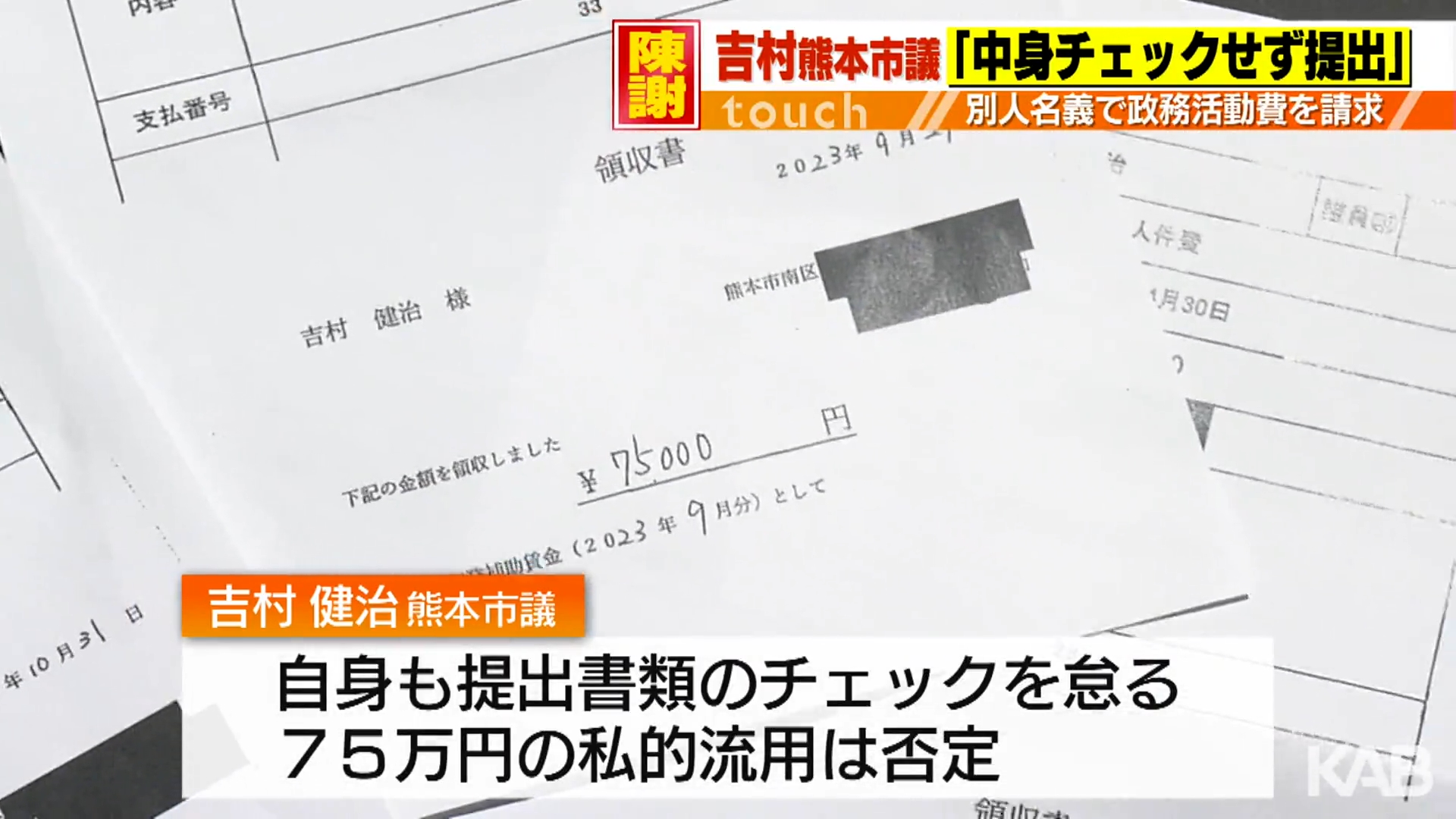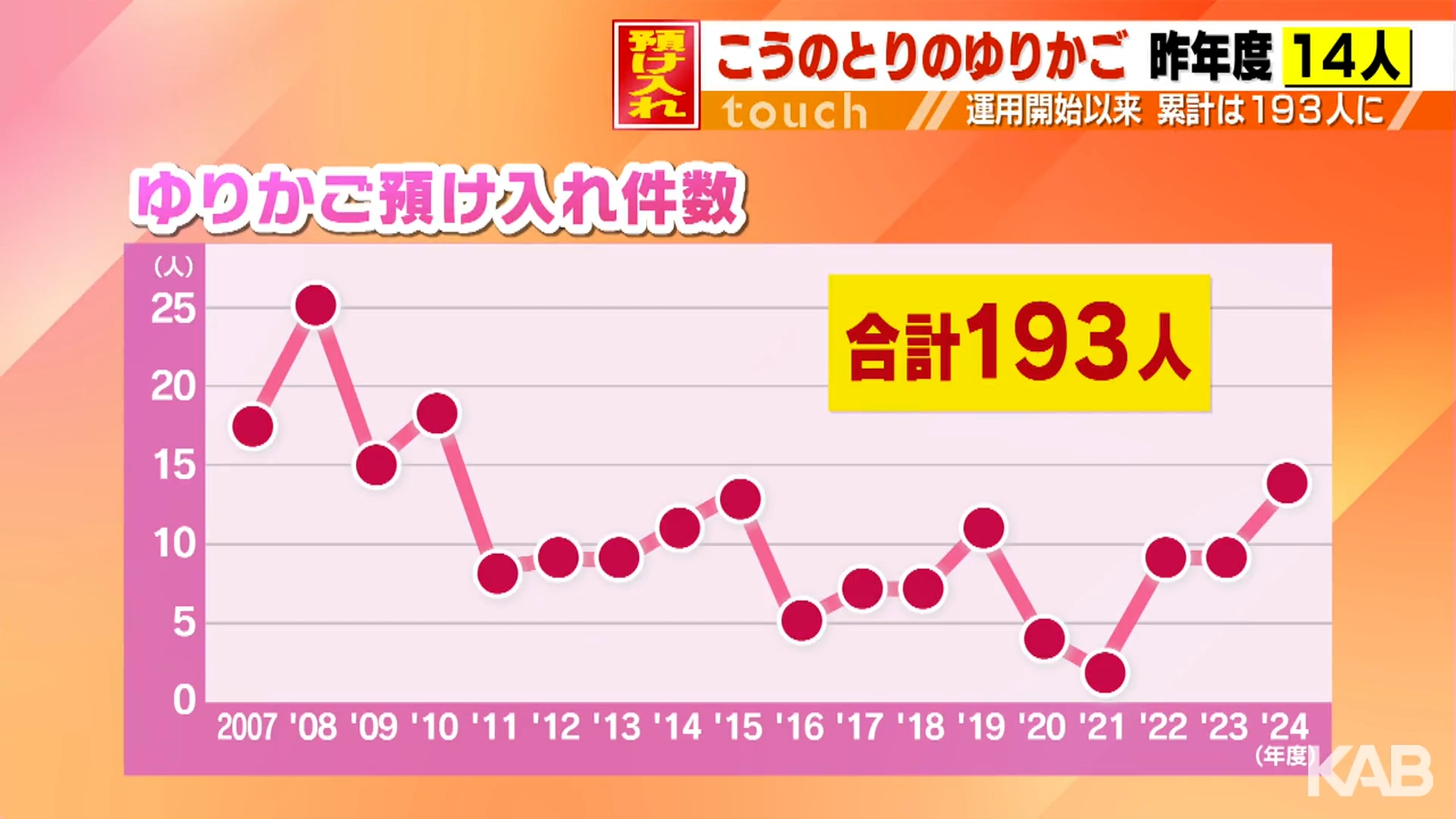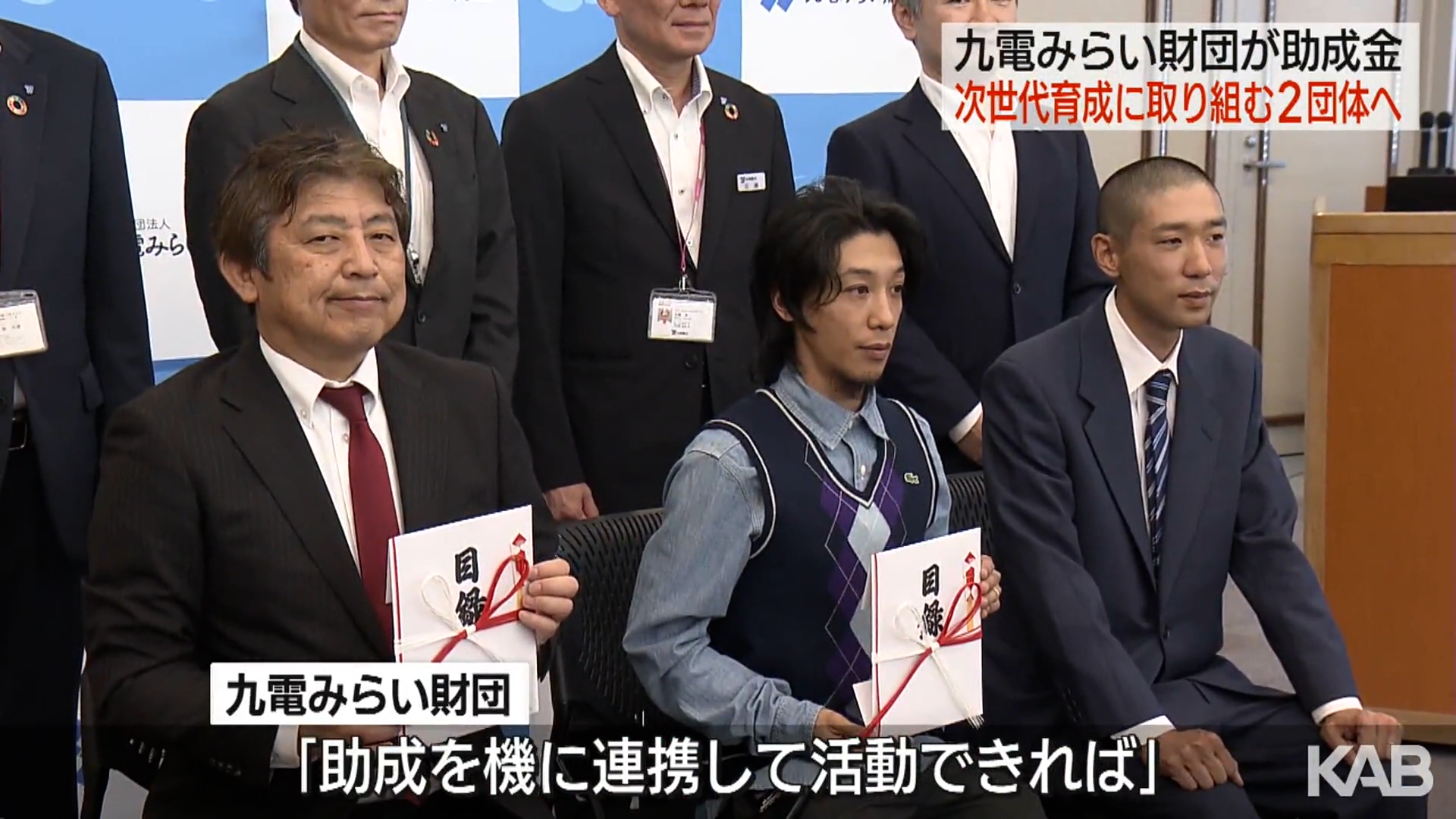飲酒運転で女性をはね、死亡させた罪に問われた被告の裁判員裁判で、熊本地裁は危険運転致死傷罪の適用を認め、求刑通り懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
井上聖貴アナウンサー
「一礼して入廷した松本被告。裁判官を真っすぐ見つめ続け、判決を聞いた後も、その姿勢を崩しませんでした」
27日に開かれた熊本地裁の法廷に、黒のスーツ姿で入廷した元飲食店従業員の松本岳被告(24)。判決によると、去年6月、熊本市中央区で飲酒運転をして車をバックで走行させるなどし、熊本市の児童相談所職員横田千尋さん(当時27歳)をはねて死亡させ、一緒にいた友人にけがを負わせたとされています。
松本被告は、午前4時16分ごろ、中央区細工町の県道を軽乗用車で走行中、眠気によって前にいたトラックに追突。飲酒運転の発覚をおそれて現場から逃走しようとして、車を時速約70キロから74キロでバックさせ車線を逆走。左側歩道にぶつかった後、急ブレーキをかけ、操縦不能になった車は歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた横田さんをはねました。
裁判では、70キロ以上のバック走行が危険運転致死傷罪の要件に当てはまるかが争点となりました。
法律の条文では「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と定められています。
これまでの裁判で、検察側は、道路状況や走行状況も踏まえて判断されるものとし「バック走行も考慮すべき」として懲役12年を求刑。一方、弁護側は要件として速度は明記されているものの「バック走行については記されていない」などと主張していました。
自動車の構造に詳しい崇城大学工学部の齊藤弘順教授は、今回の裁判で、検察側の証人としてバック走行の危険性について証言しました。
齊藤教授
「もともと停止しているところから駐車するとか、方向転換をするとか、非常に低速域での運転にしか使わない領域が想定されているので、今回のような時速70キロという高速なバック走行というのは、一般的な車両感覚を持っている人はまずいないと思います」
車は、時速70キロという高速でのバック走行を想定してないと指摘する齊藤教授。前進するのに比べて、バック走行はドライバーの視野が狭まることも、危険性の一因としています。
また、ほとんどの車に共通する特性もあります。
齊藤教授
「FF車の場合は、前輪で車が駆動します。前輪駆動車という意味合いになる」
FF車とは「フロントエンジン・フロントドライブ」の略称で、国産車の多くがこの形です。
齊藤教授
「実はFF車はバック走行で速度が速くなると、大きくオーバーステアの傾向が出ます」
質問
(思っていたよりも大きく曲がる?)
「切れる。大きく切れる状態になってしまう」
オーバーステアとは、ハンドルの切った角度に対して、より大きく内側に曲がる現象です。FF車の場合、バック走行でこの現象が起きます。そのため、およそ70キロでバック走行した場合「車両の制御は難しい」と指摘しています。
判断に注目が集まった27日の裁判。中田幹人裁判長は、松本被告の車が歩道に乗り上げた理由について、単にバック走行をしたことが原因ではなく「速度が速すぎたことで強力にオーバーステアが発生したと考えるのが合理的だ」と指摘。「進行を制御することが困難な高速度と認められる」として、危険運転致死傷罪の適用は妥当と判断。松本被告に懲役12年の判決を言い渡しました。
亡くなる1週間ほど前、生活道路での車の法定速度に関する取材で、KABのインタビューに答えていた横田さん。
横田千尋さん(当時)
「たまに危ないなというか、ここで本当に車が止まってくれるのかな、と分からないことがあるかなと思います。大体は、いつも決まったところを歩くので、気を付けるようにしています、ここ車来るかなと」
普段は、車に気をつけていると話していましたが、危険な運転の犠牲となりました。
遺族の代理人弁護士が報道陣の取材に応じ、判決後の遺族の心情を明かしました。
代理人弁護士
「遺族の率直な感想としては、今回の事故は自動車事故ではなく、殺人に等しいものだと。そういう率直な感情を述べておられました。他方で今のルールに従った判断として、危険運転致死罪の適用になることは、理屈のうえで正当なものだと納得されております」
尊い命が奪われてから、まもなく1年。事故につながる飲酒運転の根絶について、改めて考える必要があります。